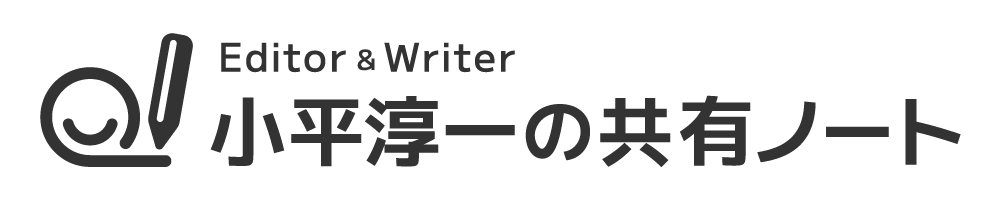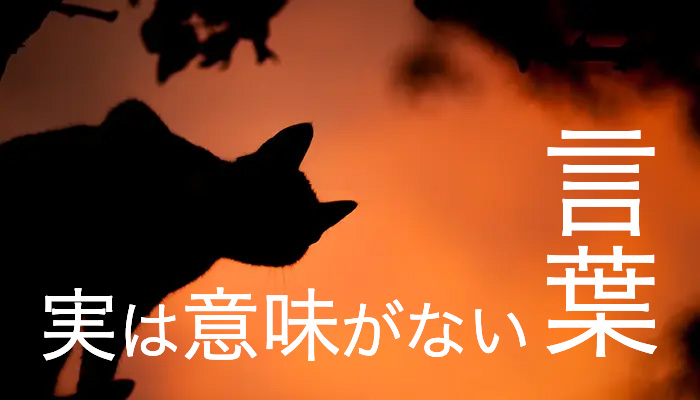何かを言っているようでいて、ほとんど意味がない言葉。僕が文章を書くときは、そんな「マジックワード」をなるべく使わないように心がけています。マジックワードを避けることは、雑誌や書籍の執筆でも、ブログやSNSでも、あるいはプレゼンやビジネスメールでも、あらゆる場面で役立つはずです。ここでは、マジックワードの具体例と回避方法を書き留めておきます。
マジックワードの意味と種類の一覧
「マジックワード」と聞くと、魔法のように便利で素敵なものだと想像するかもしれません。しかしここではそうしたプラスの意味合いではなく、「何かを表現しているようで、実は中身のない言葉」というマイナスの意味で使っています。
『その言葉だと何も言っていないのと同じです』(日本実業出版社)という書籍の中では、マジックワードを「すごく意味がありそうなのに、よく考えるとわからなくなる言葉」としています。ビジネスの場でも各種メディアの文章でも、さまざまな場所でマジックワードが使われていると指摘しています。
僕自身も、日々さまざまな文章を目にして「あ、これはマジックワードだな」と感じることがあります。その上、うっかり自分の原稿で使ってしまいそうになるときもあります。マジックワードはまるでトランプのジョーカー(ワイルドカード)のような便利さで、気を付けないとポロッと顔を出してくるのです。
とりわけ、僕が気を付けているマジックワードの一覧をまとめました。マジックワードには、次のような種類があります(各タイプの名前は、僕が勝手につけたものです)。
「なんとなく褒めておこう」タイプ
- 心地よい日差しを感じられる快適な空間
- 豊かな暮らしが手に入るグッズ
- 便利な機能が満載
- 直感的なユーザインターフェイス
- 覚えておくと重宝します
※文章の前後に、評価の根拠を言及している場合は除く
「根拠のない分類で一般化」タイプ
- 人は皆自分の過ちを認めようとしないものだ
- 使いやすさが多くの人に認められている
- 一般的に受け入れられている
- 海外ではこれが普通だ
※こちらも、文章の前後に根拠を示している場合は除く
「何かを主張しているフリ」タイプ
- 〜は検討の価値がある。
- 〜のこれからに注目したい。
- 〜なのは悩ましい問題だ。
- 〜となる可能性はゼロではない。
また、ここに挙げたもの以外に、「サスティナビリティ」や「エビデンス」といったカタカナ言葉も、マジックワードに分類されるかもしれません。ただ、あえて難解な言葉づかいをするのはマジックワード以前の話だと思うので、ここで深掘りするのはやめておきます。
「なんとなく褒めておこう」タイプの注意点
それぞれのタイプごとに、補足説明や注意点を書き留めていきましょう。まずは「なんとなく褒めておこう」タイプ。僕は特にこのタイプを警戒しています。
僕は、製品の評価記事や広告記事をよく書いています。そんなとき、ついつい印象のいい言葉を選んでしまいがちです。気づかないうちにメーカーへの忖度が出てしまったりします。しかし、安易な褒め言葉ばかりで埋め尽くしてしまうと、記事に信憑性がなくなります。
かといって、批判をすればいいというものでもありません。評価すべき点はしっかりと言及し、課題があればそれも指摘する。なるべく中立的な視点で、具体的な評価を積み重ねた記事にしたいと考えています。
「根拠のない分類で一般化」タイプの注意点
「根拠のない分類で一般化」タイプも、注意しないとつい出てきてしまいます。「人は」とか「世間では」とか「一般的には」といった表現は、その後に続く主張が一般論のような印象を与えますが、本当に根拠はあるのでしょうか。
僕はこのような根拠の希薄な一般化表現を避け、なるべく具体的な数値や根拠を示すよう注意しています(例えば、「○○%の人が○○しているというデータがある(出典:XXXX)」というような形)。
「何かを主張しているフリ」タイプの注意点
文末にひょっこりと顔を出すマジックワードにも注意が必要です。
「〜のこれからに注目したい。」や「〜なのは悩ましい問題だ。」というような結びは、結論を投げたのに近い印象があります。「注目したい」って、するのかしないのかどっち?って疑問の出る書き方ですよね。「今後に注目してほしい」と、読者にアクションを求める結論ならわかりますけど。
文章の締めがぼやけていると、最終的に何を主張しているのかが分かりにくくなります。それでは読んだ人のアクションにつながりません。自分がこの記事で何が言いたかったのかを突き詰め、シャープな結論で記事を結ぶよう心がけているつもりです。
文章は伝わらなければ意味がない
そもそも、僕がマジックワードを避ける理由は、何よりも「伝わらない」ことが問題だからです。
僕の書く記事の場合、楽しく読んでもらえたらそれでいい、というケースはごくわずかです。例えば製品の評価記事なら、自分にとって価値のある製品かどうかがハッキリわかって、価値があると判断したらすぐにでも買いに行きたくなる。そんな「読んだ人の行動につながる文章」が最高だと考えています。
あるいは、環境問題を扱った記事なら、読み手に知ってもらうだけでは不十分だと考えます。事実を知った上で消費行動や日々の生活習慣を変えてくれることまでが、僕の望むゴールなのです。
すでに述べたとおり、マジックワードは中身のない言葉です。中身のない言葉を多用して作った文章が読み手に伝わるはずがありません。自分の言いたいことが伝わらなければ、読後のアクションにもつながらないはずです。
そう考えると、やっぱりマジックワードは使わないほうが良いと思います。
(あえてマジックワードを使って読み手の思考を停止させ、言葉巧みに印象を操作するという手法もあるかもしれません。そんな手口が必要な機会は、今のところありませんが…。)
マジックワードを避ける書き方とは?
書き終えた文章を見返してマジックワードに気づいたら、可能な限り回避を試みます。
あくまで僕の場合ですが、マジックワードを使っている文章は、考えを深掘りしきれていないケースがほとんどです。例えば、なにかアプリの紹介記事を書いていて、「無料なのに高機能」というフレーズを書いてしまったとします。これを見つけたとき、僕はこんな風に自問自答を試みます。
「高機能って多機能という意味? だったら多機能と書けばいいのでは? でも、本当に多機能なのがいいことなの? このアプリで僕が本当にオススメしたいのは、いろいろな機能が揃っていること? それよりも、もっと何か特筆すべきポイントがあるのでは…?」
深みにハマると、すべてをイチから書き直したいと思うこともあります。時間をかけて書いたものをバッサリ切り捨てるのは未練が残りますが、「責任を持って送り出せる文章にしよう!」と自分を奮い立たせます。
自分を縛りすぎても不自由になる
いろいろと偉そうに書いてきましたが、僕自身も決して模範的な文章が書けていたわけではありません。これまで何度も、マジックワードを使った文章を書いてしまったと思います。しかも大昔ではなく、ごく最近のことかもしれません。
なにしろ、マジックワードはとにかく「便利なフレーズ」で、真意を伝えようとすると文字量も増えてしまいがちです。文字量が限られた雑誌の記事では、マジックワードだと認識しながらつい見逃してしまったこともあると思います。
僕自身、文章の書き方はまだまだ勉強中ですが、あえて「文章術」と銘打ってブログのネタにすることで自戒につながり、たまたま訪れた誰かの役にも立つのではないかと考えました。
「あれはダメ、これはダメ」と縛りすぎると、文章を書くのがつらくなってしまうと思います。「マジックワードはNG」という考え方ではなく、「もし自分の文章で見つけたら、一度自分の中で考え直してみよう」という書き方の提案として捉えていただけると幸いです。
文章術を鍛えるのにおすすめの一冊
最後に、文章術の向上を目指している同志の皆さんに本を一冊お勧めしておきます。『「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。』(藤吉 豊、小川 真理子 著 日経BP 刊)は、膨大な文章術の本を研究し、多くの人が指摘している文章作成のポイントを1冊にまとめています。
これから本格的に文章を書いていこうという人から、ライターなど文章を生業にしている人まで、あらゆる人におすすめしたい一冊です。ここ数年で読んだ文章術の本の中で一番のヒットでした。ご興味あればぜひご一読ください。